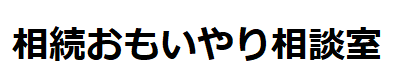遺言書の「生前行為・抵触行為等」による撤回擬制‥大審院・最判で解釈は落ち着き
1.遺言の撤回と撤回擬制
民法は,次の2条にあるような一定の事実が存在する場合には,遺言者の真意いかんを問わず、遺言の撤回があったものと擬制している。
■第一〇二二条(遺言の撤回)
遺言者は、いつでも、遺言の方式に従って、その遺言の全部又は一部を撤回することができる。
■第一〇二三条(前の遺言と後の遺言との抵触等)
前の遺言が後の遺言と抵触するときは、その抵触する部分については、後の遺言で前の遺言を撤回したものとみなす。
2前項の規定は、遺言が遺言後の生前処分その他の法律行為と抵触する場合について準用する。
通常これらの事実が存在する場合には,遺言者は撤回の意思があるのと推定しうるし,かかる意思が存在しない場合でもあらかじめ争いの生ずるのを避け,遺言者の最終意思の実現を期するため,撤回を擬制したものである。
時日を異にした前後2個の遺言がある場合,死亡に近い後の遺言は,遺言者の最終意思を尊重することから後遺言を優先せしむべきことは,遺言の性質上当然である。これを「後遺言優先の原則」という。
2.前の遺言が後の遺言と抵触する「抵触」解釈の判例の立場
抵触の有無の程度は,事実問題であるが,形式的に決定すべきではなく,遺言の解釈によりその全趣旨から決定され両遺言の内容を実現することが客観的に絶対不可能であることを要しない。判例は「前ノ遺言ノ執行が不能ト為ルガ如キ場合ノミ二止マラズ、諸般ノ事情ヨリ観察シテ後ノ行為が前ノ遺言ト之ヲ両立セシメザル趣旨ノ下ニ為サレタルコト明白ナル場合モ包含スル」(大判昭18.3.19 民集22.185,同旨:東京地判昭53-1-25判タ363-268) としている。抵触するか否か,全部抵触か一部抵触かは,專ら遺言書の全趣旨から判断されねばならない(大判昭12.7)。
3.「抵触する生前行為」とは
(1)遺言の方式による意思表示を必要とするという原則の緩和
もともと民法の原則で行けば、前の遺言を撤回する遺言をして前の遺言を失効せしめ, ついで生前処分その他の法律行為をすべきであるが、遺言者がいきなり前の遺言と抵触する行為をした場合にも, そこに撤回の効力を擬制した。
①遺言書の意思に基づく場合
生前処分ないし法律行為が撤回権を有する遺言者自身によってされずに、遺言者の法定代理人による抵触行為や遺言者の債権者による強制続売、目的物収用、他人の不法行為による滅失等は撤回とされない。また、遺言者が生前行為を他人に委任して代理権を授与し,この任意代理人によって生前行為がなされたときは,遺言者自身の
なした場合と同視すべきである。
②生前処分とは,
・遺贈の目的である特定の権利や物についての生前行為として,所有物の譲渡,寄附行為,特定債権の弁済受領等
・売買 交換等の債権契約の締結, 祭祀主宰者の指定 (897) その他身分行為, 死因贈与等
・ 終生の扶養を受けることを前提として養子縁組をしたうえ,その所有不動産の大半を養子に遺贈する旨の遺言をした者が,その後養子に対する不信の念を強くしたため, 協議離縁をし, 法律上も事実上も扶養を受けないことにした場合,その離縁により遺贈は撤回されたものである(最判昭 56·11· 13民集35·8.1251)。
③「抵触」解釈
基本は上記大判昭18.3.19と同じであるが、前の遺言を失効させなければそれらの行為が有効となりえないことをいい, たとえば, 先に甲に遺贈した不動産を後に乙に贈与する場合などである。しかし, 必ずしも後の行為によって前の遺言が法律上または物理的に全く執行不能となった場合に限られず, 後の行為が前の遺言と両立させない趣旨でなされたことが明白であればよいので、抵触するか否かおよびその範囲は、一方,遺言の解釈の問題であると同時に, 他方, それらの行為の解釈の問題である。要するに, これらの全事情を合理的に判断したうえで決すべきである。包括遺贈後,遺贈者がその財産の属する特定の物または権利を生前処分しても,包括遺贈と抵触するものではない。
地裁判例ではあるが、「母が,全遺産を長女に遺贈する遺言をした後,二女にも相続分があることを認め,その趣旨で金銭支払の和解をした場合について,和解契約の履行により必ずしも前記遺贈の執行が不能となるわけではないが,本件和解はそれと両立せしめない趣旨でなされたるのと認定して,先の遺贈は撤回された」とする東京地判昭53. 1がある。
なお、主務官庁の認可が停止条件となる事例において最高裁は、「遺言による寄附行為に基づく財団法人の設立
行為がなされたあとで, 遺言者の生前処分の寄附行為に基づく財団設立行為がされて, 両者が競合する形式になった場合において, 右生前処分が遺言と抵触し,したがって, その遺言が取り消されたものとみなされるためには、少なくとも, まず, 右生前処分の寄附行為に基づく財団設立行為が主務官庁の許可によって, その財団が設立され, その効果の生じたことを必要とする」とする(最判昭 43- 12.24)。学説は、寄付自体で抵触があったとして反対が多く私もその方が遺言者の意思に近く妥当と解するのである。
(2)最新の判例から
【平成2年2月28日 大阪高等裁判所】
一 特定の財産を共同相続人の一人に「相続させる」旨の遺言は、遺言者の意思が明確に遺贈であると解されない限り、遺産分割方法の指定と解するのが相当である。
二 特定の財産を共同相続人の一人に「相続させる」旨の遺言により遺産分割方法の指定がされた場合、右共同相続人が当該財産を取得する意思を表明したときは、右共同相続人は、遺産分割の協議又は審判を経るまでもなく、その所有権を取得する。
三 数筆の土地を共同相続人の一人に相続させる旨分割方法を指定した遺言の後に遺言者がした同土地の合筆及び分筆の登記手続は、右遺言と抵触するものではない。
【平成9年11月13日 最高裁判所第一小法廷】
一 遺言者が遺言を撤回する遺言を更に別の遺言をもって撤回した場合において、遺言書の記載に照らし、遺言者の意思が当初の遺言の復活を希望するものであることが明らかなときは、当初の遺言の効力が復活する。
二 遺言者が、甲遺言を乙遺言をもって撤回した後更に乙遺言を無効とし甲遺言を有効とする内容の丙遺言をしたときは、甲遺言の効力が復活する。
投稿者プロフィール

最新の投稿
 財産管理2023年11月12日実務家のための相続財産の調査【令和5年最新版】
財産管理2023年11月12日実務家のための相続財産の調査【令和5年最新版】 遺産分割2023年5月21日【遺産分割10年規制】とは? 相続法の改正 令和5年4月1日施行
遺産分割2023年5月21日【遺産分割10年規制】とは? 相続法の改正 令和5年4月1日施行 相続全般2023年4月13日相続人間の相続分譲渡は遺留分算定の対象になるか
相続全般2023年4月13日相続人間の相続分譲渡は遺留分算定の対象になるか 相続全般2023年4月12日『信託契約』で貴重な財産を受託者から取り返せなくなった事例…民法も解っていない士業が税務も含めた信託法実務が解るわけがない
相続全般2023年4月12日『信託契約』で貴重な財産を受託者から取り返せなくなった事例…民法も解っていない士業が税務も含めた信託法実務が解るわけがない