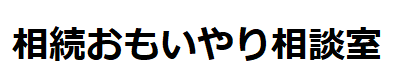1.遺言書の内容に少しでも疑義があれば銀行等は支払わないのが原則
(1)銀行の基本的姿勢
「遺言者の法定相続人の確定」は、相続実務の経験あるベテランの銀行員だと、戸籍謄本の「繋ぎ」日時の確認からスムーズにやり始める。
しかし、このような職員は相続おもいやり相談室代表の当職の経験で言うと、地銀以上で、店舗カウンターから3列以上の奥に座っている銀行員でないと無理である。それでも限られた人材にしか無理である。実は、遺言信託や遺言執行業務などを当行ではやりますといってもなかなか厳しいものがある。その一方で若手の女性職員で相当相続に明るいものがいたりもするが。
そのうえで、相続人となっている確定された法定相続人や、法定相続人ではない受遺者がいたときにその受遺者を含む、全員の意思に基づく払戻請求として、全員の署名・捺印のある銀行の様式の書面による払戻請求(または全員の署名・捺印のある遺産分割協議書等に基づく払戻請求)があれば、払い戻しに応じてくる。
なお、遺贈による払い戻し請求の時には、請求者が遺言によって指定された受遺者で、その受遺者が請求の対象である預貯金を取得することが遺言によって明確に定められていると解釈できれば払い戻しに応じてくる。
この場合も、数回の銀行等の東京等にある「相続センター」とのやり取りがあるので、ざっと2時間はかかる。
当職も、銀行等へ遺言執行者で行くときはもう半日仕事になってしまうのだ。数行の掛け持ちはいつも「しんどい」のだ。
これに証券会社などが加わってくると、一日がそれで終了である。他の仕事はほぼ出来ないのだ。
なお、「預貯金残高の照会」は、実務上は法定の権利を持つものは銀行等は応じている。つまり、法定相続人ばかりでなく、遺言の内容から受遺者と判断される者、遺言執行者からの請求についても、その業務に必要な範囲で、応じる。
(2)「嫁の○山○子が世話をしてくれるので、私の物は全部○子にあげます。」遺言は払戻す?
この場合に、通常は銀行は通帳はもちろん、除籍謄本を筆頭に、身分関係のわかる書類を強く要求してくる。「嫁」は誰のことさすのか確定できるか、自筆時に遺言能力はあったのか等が曖昧で簡単には払い戻しに応じないであろう。
また、疑念があれば、調査するときに遺族は遺言の内容に直接的・間接的に利害を有していることがあるため、自分に都合のいいように言っているかもしれないので話を聞いてくれても客観的な資料がないと難しい。
(3)「○○銀行○○支店の普通預金(口座番号…‥)を、○山○子に相続させる/遺贈する。」
このような明確な遺言では、ほぼ確実に払戻されるであろう。
(4)「私の財産の全部を、孫・○山○子(平成○年○月○日生)に相続させる/遺贈する。」
も(3)と同様である。
(5)「私の財産の全部を、姪・○山○子(平成○年○月○日生)と甥・○川○男(平成○年○月○日生)に与えます。」
このように、複数の者が指定されている場合にも、受遺者が明瞭に特定できる場合は複数受遺者の意思を確認して、遺言者の法定相続人の確定を経ずに、或いは他の法定相続人全員の意思によらず払戻されるであろう。2人へは公平に同じ割合と言う事になろう。補充解釈、遺言有効解釈、被相続人の意思尊重の観点があろう。
(6)「私の財産の全部を、お世話になった叔母さんに遺贈します。」の自筆の遺言で叔母を名乗る者が払戻しを請求した場合
銀行等はこの請求者が本当に遺言者の叔母なのかを戸籍などによって確認しないとそもそも話は進まない。しかし、単に「叔母」では複数いる可能性がありお世話になった叔母なのかどうか不明であろう。詳細な戸籍調査をしてくる。それが終わらないとこの遺言では難しいであろう。
さらに漢字の「叔母」でなくてひらがなの「おばさん」だと不明度は高まってくるので簡単ではない。
同じく、「私の財産の全部を、○子にあげます。」遺言では、姓名の名だけではとても特定は難しく、間接証拠で個人が特定されて固まらないと銀行等の払出は限りなく透明に近く無理だ。
(7)「私の財産のうち半分を、○山○子のものとする。」遺言
これは他の半分を誰が取得するのか確定しないと難しい。
そもそも、この遺言は、○子さんが法定相続人であれば包括遺贈または相続分の指定であり、法定相続人でなければ包括遺贈となるが、他の半分については遺言者の意思が不明である。
法定相続人を確定したうえ、他の法定相続人との遺産分割を経なければ遺言が持ち込まれた金融機関の預貯金を法定相続人・受遺者のうち誰が取得するか判定することができないため、来店された受遺者のみによる払戻請求には応じないことはほぼ間違いない。残念だが、如何ともし難い。
2.指定された受遺者が死亡していた場合
これが無効になることがあるとすると皆さんは驚くかも知れないが、公正証書遺言でも専門家でない法律家が原案を作り、公証人が中途半端である「ヤバい」遺言は結構あるのだ。代襲相続にもならない場合だ。
通常は、予備遺言条項と言って、次のように受遺者が死亡していた場合に備えた定めを設ける。「私の財産の全部を、子・○山○子(昭和○年○月○日生)に相続させる/遺贈する。」に続け、「私が死亡する以前に○山○子が死亡していた場合、遺言者の財産の全部を孫・○山○男(平成○年○月○日生)に相続させる/遺贈する。」と原案をするのだ。
しかし、自筆証書遺言等ではまずここまで書かない場合が多い。
そうすると、前述のように無効となって、当該無効となった部分の対象である遺産は、遺言の他の定めに従って処理され、他の定めもなければ、法定相続の対象となり、法定相続人を確定したうえ、相続分に応じて法定相続人の遺産分割の対象となる。
念のために申すと、全部無効の遺言と解釈するのはナンセンスだ。
3.預金についての遺言がある場合のケースバイケース判断
(1)「○○銀行○○支店の預金全部を、○山○子に相続させる/遺贈する。」、「○○銀行の預金全部を、○山○子に相続させる/遺贈する。」、「金融機関の預貯金全部を、○山○子に相続させる/遺贈する。」、「私の遺産全部を、○山○子に相続させる/遺贈する。」などは、大丈夫で銀行等は払い戻しに応ずるであろう。
(2)「金融機関の預貯金のうち1000万円を、○山○子に与える。」遺言では、払い戻しが難しい。
この遺言は、1000万円までであれば、○山○子さんの払戻請求に応じてよいと解することが一見できるが、すでに他の金融機関で1000万円の払戻しを受けている可能性があるからだ。これの実現はかなり困難であろう。なんとも遺言者と受遺者にはお気の毒であるが。
4.条件付き遺贈・負担付き遺贈
この場合は、その条件や負担を確定する必要があるのでそのままの支払いはない。もっとも、厳格に条件とせずに、「長女の○山○子が世話をしてくれるので、私の物は全部○子にあげます。」とあれば、経緯の記載としてもいいだろう。払い出しする銀行等が多いのではないかな。
5.遺留分侵害額請求(改正相続法)
(1)改正前の相続法
改正前の民法が適用されるときは、受遺者でない法定相続人から、遺留分減殺請求権を行使したので受遺者に払い戻さないでほしい、つまり遺留分相当額を私に払い戻して欲しいとの申し出があると、遺留分減殺請求権の行使によって遺言は遺留分の範囲で無効となるため、遺言の内容に応じた支払いは銀行等は慎重であった。
(2)改正後の相続法
改正後の民法では、遺留分侵害額請求権の行使があっても、遺言の効力には影響がなくなった(民法1046条)。 よって、2019年7月以降に相続が開始された場合に、遺留分侵害額請求権の行使にかかわらず、銀行等は前述のように対応してくる。
6.遺言執行者による払戻請求
(1)遺言によって、遺言執行者に預貯金の払戻しを請求する権限を与える旨が明記されている場合
相続おもいやり相談室の当職が原案を作る遺言書(公正証書遺言や自筆証書遺言等)は、ほぼこの明記があるが、銀行等は遺言執行者への信頼から、これまでの経験で言うとかなり迅速に預貯金の解約・払戻しをする。
場合によっては、複数の遺言執行者を選任する場合もあるが、そのうちある者にのみに預貯金の払戻しを請求する権限を与える旨が定められている場合もあるから、銀行等はそれを身分証明書や住民票などで確認してくる。
(2)遺言によって、遺言執行者に預貯金の払戻しを請求する権限を与えるかどうか明記されていない場合
これも相続相談で当職によく持ち込まれることが多い。この場合は、遺言執行者に払い戻された預貯金が真の権利者に交付されず、金融機関が二重払いを強いられる可能性があるので、払い戻しに応じないことが多いであろう。
なお、遺言の法律解釈になるが、「遺言執行者は遺産を換価して債務を弁済し、その余を等分にて長男の○山○男と、長女の〇川〇子のものとする。」とあれば、遺言執行者に預貯金の払戻しを請求する権限を与える意思があるとして払い戻しに応ずるであろう。
(3)遺言執行者の権限強化に関する改正相続法の影響
「OO銀行OO支店の普通預金(口座番号○○)を、○山○子に相続させる/遺贈する。」とする遺言の場合に、遺言執行者に払戻しの権限があるかどうかは、これまではっきりしていなかったが、2019年7月以降に遺言が作成された場合、特定の遺産を法定相続人の一部に与えるもの(特定財産承継遺言)であれば、当該遺言の実現に必要な範囲内で遺言執行者に払戻しの権限があるものとされるようになった(民法1014条3項)。
…………………………………………………………………………………………………………………
第一〇一四条(特定財産に関する遺言の執行)
前三条の規定は、遺言が相続財産のうち特定の財産に関する場合には、その財産についてのみ適用する。
2遺産の分割の方法の指定として遺産に属する特定の財産を共同相続人の一人又は数人に承継させる旨の遺言(以下「特定財産承継遺言」という。)があったときは、遺言執行者は、当該共同相続人が第八百九十九条の二第一項に規定する対抗要件を備えるために必要な行為をすることができる。
3前項の財産が預貯金債権である場合には、遺言執行者は、同項に規定する行為のほか、その預金又は貯金の払戻しの請求及びその預金又は貯金に係る契約の解約の申入れをすることができる。ただし、解約の申入れについては、その預貯金債権の全部が特定財産承継遺言の目的である場合に限る。
…………………………………………………………………………………………………………………
(4)遺言執行者が死亡していた場合
就任前に遺言執行者が亡くなったり、遺言執行者が就任した後、不慮の事故によって遺言執行者が亡くなったりすることもある。当職もあり得ることであるのは間違いない。
この場合に、すでに遺言執行者が亡くなっているのであれば、遺言のうち遺言執行者の指定に関する部分は無効である。
また、就任後に遺言執行者が亡くなったのであれば、その時点で遺言執行者の任務は終了するが、その地位は、遺言執行者の法定相続人が相続しない。
そうすると、遺言執行者がいない状態で、遺言者の法定相続人が遺言を執行することになろう。しかし、利害関係人の請求によって家庭裁判所が遺言執行者を選任する場合もあり得る。
なぜなら、受遺者等が、遺言執行の公正さを担保したい場合もあるからである。
(5)遺言執行者の権限の明確化に関する改正相続法と復任権・使者による払い戻し請求
遺言によって、遺言執行者が第三者に遺言執行を行わせてよい旨が明記されていないときであっても、2019年7月以降に遺言がされた場合、遺言執行者は第三者に遺言執行を行わせることができるようになった(民法1016条1項本文)。ただし、遺言に、遺言執行者が第三者に遺言執行を行わせたくないという遺言者の意思が表示されているときは、この限りではない(同項但書)。
その結果、これまでの実務と同じように、遺言執行者の名義で手続を行う使者にすぎないものが来たときはその地位を確認したうえ、遺言執行者本人による手続として取り扱っていいが、復任の場合、遺言によって、遺言執行者が第三者に遺言執行を行わせてよい旨が明記されているときばかりでなく、その旨の明記されていないときであっても、2019年7月以降に遺言がされた場合、遺言執行者は第三者に遺言執行を行わせることができるので銀行等は払い戻しに応じる。
7.法定相続人全員の意思に基づく払戻請求
当職もしばしば直面するのであるが、遺言者の法定相続人や、法定相続人ではない受遺者がいたときにその受遺者を含む、全員の意思に基づく払戻請求の際、遺言と異なる内容の遺産分割協議がされることがある。不労所得に血眼になる欲深い魑魅魍魎が出てきてほぼ進退窮まるほどのダメージを受けることがある。
この厄介なことは、遺言によって遺産分割協議が禁止されている場合は、かかる遺産分割協議が無効とされようが、しばしこの付記的記述が遺言の本文にないのだ。
この時に、遺言執行者はその法的立場や事実上の権限行使がこれらのものによって弱くなってしまう。そこで、上記のような権限強化が改正相続法でなされているのだが、協議に入ってその内容に関与することはできないかもしれないが、少なくとも同意権限はあるのでないかというのが当職の現在の持論である。
遺言本質論にもかかわることであるが、憲法の私有財産制や民法の財産に関する規定を見ても、本来自分の財産は死ぬにあたってその者の好きに処分していいはずだ。その意思を実現するのが遺言執行者ではないのか。
銀行等は、遺言者の法定相続人や、法定相続人ではない受遺者がいたときにその受遺者を含む全員が、遺言と抵触する遺産分割協議の結果を署名等の体裁を整えて持参すれば、遺言執行人の意見を聞いて支払うべきであろう。
金融機関がトラブルに巻き込まれるおそれは大きくない、というリスク判断は当職は賛成できない。この点の訴訟も過去に起きてもいる。
8.遺言の国際私法としての準拠法
日本滞在の外国人が増えて、相続規範をいずれの国の法律に基づいて解決するかという渉外関係においては、「遺言の成立及び効力は、その成立の当時における遺言者の本国法による」とされている(法の適用に関する通則法37条1項)。
日本の法以外の国・地域の法が適用される場合は、その本国法において預貯金の払戻しを請求する権限を有することの意見書を弁護士に作成してもらう。弁護士はその意見書の前提となる事実の存在を証明する資料や外国語で書かれた資料であれば訳文を提出する。
また、地域により法が異なる場合には当該国の規制に従い指定される地域もしくは国際私法の一般原則である最も密接な関係がある地域の法が適用される。また、反致があって、その国の法律によって、遺言においては日本法を適用することを表示していればそのとおりに取り扱ってよい。もっとも二重反致の場合もある。
投稿者プロフィール

最新の投稿
 お知らせ2025年5月13日中川総合法務オフィスは統合サイトに全て移行中。
お知らせ2025年5月13日中川総合法務オフィスは統合サイトに全て移行中。 相続全般2025年4月2日相続(特に遺産分割)におけるエンバーミングの必要性
相続全般2025年4月2日相続(特に遺産分割)におけるエンバーミングの必要性 相続全般2025年2月28日世話していた独身の叔父さんが2億円を残して急死。いとこが何人いるか不明。どうすればいいのか【相続実例】
相続全般2025年2月28日世話していた独身の叔父さんが2億円を残して急死。いとこが何人いるか不明。どうすればいいのか【相続実例】 相続全般2025年2月9日墓のある相続土地の売却方法は4つほどある:相続おもいやり相談室
相続全般2025年2月9日墓のある相続土地の売却方法は4つほどある:相続おもいやり相談室