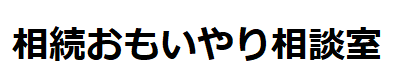5.遺留分減殺請求から遺留分侵害額請求制度に変更
(1)遺留分減殺請求権の行使による物権的効果廃止
相続法改正は、遺留分の侵害を主張しても「金銭」を請求できるのみとなって、実務的には非常にすっきりした。
…………………………………………………………………………………………………………………
第一〇四六条(遺留分侵害額の請求)
遺留分権利者及びその承継人は、受遺者(特定財産承継遺言により財産を承継し又は相続分の指定を受けた相続人を含む。以下この章において同じ。)又は受贈者に対し、遺留分侵害額に相当する金銭の支払を請求することができる。
2遺留分侵害額は、第千四十二条の規定による遺留分から第一号及び第二号に掲げる額を控除し、これに第三号に掲げる額を加算して算定する。
一 遺留分権利者が受けた遺贈又は第九百三条第一項に規定する贈与の価額
二 第九百条から第九百二条まで、第九百三条及び第九百四条の規定により算定した相続分に応じて遺留分権利者が取得すべき遺産の価額
三 被相続人が相続開始の時において有した債務のうち、第八百九十九条の規定により遺留分権利者が承継する債務(次条第三項において「遺留分権利者承継債務」という。)の額
…………………………………………………………………………………………………………………
この改正は遺言者の意思を尊重する優れたもので、相続人間で不動産の共有関係が当然に生じていた事態を避けることができ、遺言によって特定の財産を相続人や受遺者に与えたいという遺言者の意思が尊重される。
また、承継される「株式」が準共有状態になって株主名簿に登録されるという、複雑な権利関係が発生することもなくなる。
(2)受遺者が複数いる場合
遺留分侵害額請求により、受遺者は、遺贈(特定財産承継遺言による財産の承継を含む)の目的の価額(受遺者が相続人である場合は、同人自身にも遺留分があるから、当該価額から遺留分として同人が受けるべき額を控除した額)を限度として、各人の受けた遺贈の目的の価額の割合に応じて、それぞれ遺留分侵害額を負担することに変更された。
第一〇四七条(受遺者又は受贈者の負担額)
受遺者又は受贈者は、次の各号の定めるところに従い、遺贈(特定財産承継遺言による財産の承継又は相続分の指定による遺産の取得を含む。以下この章において同じ。)又は贈与(遺留分を算定するための財産の価額に算入されるものに限る。以下この章において同じ。)の目的の価額(受遺者又は受贈者が相続人である場合にあっては、当該価額から第千四十二条の規定による遺留分として当該相続人が受けるべき額を控除した額)を限度として、遺留分侵害額を負担する。
一 受遺者と受贈者とがあるときは、受遺者が先に負担する。
二 受遺者が複数あるとき、又は受贈者が複数ある場合においてその贈与が同時にされたものであるときは、受遺者又は受贈者がその目的の価額の割合に応じて負担する。ただし、遺言者がその遺言に別段の意思を表示したときは、その意思に従う。
三 受贈者が複数あるとき(前号に規定する場合を除く。)は、後の贈与に係る受贈者から順次前の贈与に係る受贈者が負担する。
2第九百四条、第千四十三条第二項及び第千四十五条の規定は、前項に規定する遺贈又は贈与の目的の価額について準用する。
3前条第一項の請求を受けた受遺者又は受贈者は、遺留分権利者承継債務について弁済その他の債務を消滅させる行為をしたときは、消滅した債務の額の限度において、遺留分権利者に対する意思表示によって第一項の規定により負担する債務を消滅させることができる。この場合において、当該行為によって遺留分権利者に対して取得した求償権は、消滅した当該債務の額の限度において消滅する。
4受遺者又は受贈者の無資力によって生じた損失は、遺留分権利者の負担に帰する。
5裁判所は、受遺者又は受贈者の請求により、第一項の規定により負担する債務の全部又は一部の支払につき相当の期限を許与することができる。
…………………………………………………………………………………………………………………
いずれにしろ、例外的であれ、「現物引渡し」を求めることはできなくなった。
当事者が合意すれば、不動産を含む財産を遺留分侵害額請求に基づく金銭に代えて現物給付ができるが、この場合、「代物弁済」となって、受遺者に譲渡所得税がかかる。
もっとも受遺者からみれば、請求者に現物を押し付けることはできなくなり、金銭で払わざるを得なくなったともいえる。
(3)遺留分の算定方法の改正
これまで、贈与は相続開始前の1年間にしたものに限り、遺留分の算定の規定によりその価額を算入するとされていた(改正前民法1030条前段)が、実務においては、最高裁判所判例により、旧条項が民法903条を準用するとされていたためである(最判平成10・ 3 ・24)。
第九〇三条(特別受益者の相続分)
共同相続人中に、被相続人から、遺贈を受け、又は婚姻若しくは養子縁組のため若しくは生計の資本として贈与を受けた者があるときは、被相続人が相続開始の時において有した財産の価額にその贈与の価額を加えたものを相続財産とみなし、第九百条から第九百二条までの規定により算定した相続分の中からその遺贈又は贈与の価額を控除した残額をもってその者の相続分とする。
つまり、判例は、民法903条1項の定める相続人に対する贈与は、当該贈与が相続開始よりも「相当以前」にされたものであって、その後の時の経過に伴う社会経済事情や相続人など関係人の個人的事情の変化をも考慮するとき、減殺請求を認めることが当該相続人に酷であるなどの特段の事情のない限り、同法1030条の定める要件を満たさないものであっても、遺留分減殺の対象となるとしていた。
これらの点を踏まえて、今回の法改正で次のように整理された。
第一〇四三条(遺留分を算定するための財産の価額)
遺留分を算定するための財産の価額は、被相続人が相続開始の時において有した財産の価額にその贈与した財産の価額を加えた額から債務の全額を控除した額とする。
2条件付きの権利又は存続期間の不確定な権利は、家庭裁判所が選任した鑑定人の評価に従って、その価格を定める。
第一〇四四条
贈与は、相続開始前の一年間にしたものに限り、前条の規定によりその価額を算入する。当事者双方が遺留分権利者に損害を加えることを知って贈与をしたときは、一年前の日より前にしたものについても、同様とする。
2第九百四条の規定は、前項に規定する贈与の価額について準用する。
3相続人に対する贈与についての第一項の規定の適用については、同項中「一年」とあるのは「十年」と、「価額」とあるのは「価額(婚姻若しくは養子縁組のため又は生計の資本として受けた贈与の価額に限る。)」とする。
なお、依然として特別受益の問題は残るので、実務でよく使う遺言等で持戻し免除の定めをすることになろう。
つまり、被相続人が遺言で「持戻し免除」の意思表示をすれば、特別受益を相続財産に加えられることはなくなる。
ところで、1044条1項では、「…当事者双方が遺留分権利者に損害を加えることを知って贈与をしたときは、1年前の日より前にしたものについても、…」とあるが、この「害意」の「害意」の立証は、困難を極めることがある一方で、安易に主張されることもありうる。
遺言者が将来、相続トラブルの発生を避け、相続人間の公平を図りたいときは、遺言書の付言事項等で生前贈与のいきさつや、実はそれが贈与でなく貸付金であるなどの事情を明らかにすべきで、場合によっては、903条3項の持戻しの免除の適用を考えることも必要である。
(4)裁判所による債務弁済支払いの猶予の許与制度
遺留侵害額請求権になった関係で、受遺相続人が遺留分を現金で支払うことが直ちに出来ない場合も多く出てくるであろう。
そこで、裁判所による債務弁済の支払いの猶予の許与制度を導入した。これにより、受遺相続人において、分割払いや支払期間の猶予という方法で負担を軽くすることができるようになった。
■1047条第5項:裁判所は、受遺者又は受贈者の請求により、第一項の規定により負担する債務の全部又は一部の支払につき相当の期限を許与することができる。
投稿者プロフィール

最新の投稿
 お知らせ2025年5月13日中川総合法務オフィスは統合サイトに全て移行中。
お知らせ2025年5月13日中川総合法務オフィスは統合サイトに全て移行中。 相続全般2025年4月2日相続(特に遺産分割)におけるエンバーミングの必要性
相続全般2025年4月2日相続(特に遺産分割)におけるエンバーミングの必要性 相続全般2025年2月28日世話していた独身の叔父さんが2億円を残して急死。いとこが何人いるか不明。どうすればいいのか【相続実例】
相続全般2025年2月28日世話していた独身の叔父さんが2億円を残して急死。いとこが何人いるか不明。どうすればいいのか【相続実例】 相続全般2025年2月9日墓のある相続土地の売却方法は4つほどある:相続おもいやり相談室
相続全般2025年2月9日墓のある相続土地の売却方法は4つほどある:相続おもいやり相談室