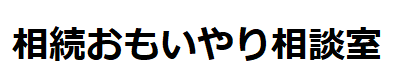6.遺産分割前の仮払い制度の創設
(1)預貯金債権が遺産分割の対象に含まれるとする最高裁判例の影響と法改正
非常に大きな実務への影響を及ぼした最決平成28・12・19は、当然相続人に債権が分割されるとした実務を変更して「預貯金債権が遺産分割の対象に含まれる」と判断して、相続人は遺産分割が終了するまでは単独で預貯金の払戻しを受けることができず、相続人全員で行使しなければならなくなった。
しかし、それでは、相続人中に遺産分割に反対する人がいる場合に、被相続人の葬儀代や入院費、相続人の当面の生活費などを工面できずに困ることかある。そこで法改正により、家事事件手続法200条の保全処分の要件を緩和し、相続人が家庭裁判所に対して、遺産分割前の預貯金の仮払いを申し立てられるようになった。
同条3項において「遺産の分割の審判又は調停の申立てがあった場合において、相続財産に属する債務の弁済、相続人の生活費の支弁その他の事情により遺産に属する預貯金債権を当該申立てをした者又は相手方が行使する必要があると認めるときは、その申立てにより、遺産に属する特定の預貯金債権の全部又は一部をその者に仮に取得させることができる、ただし、他の共同相続人の利益を害するときはこの限りではない」旨が規定された。
(2)家庭裁判所の判断を経ずに預貯金の払戻しも可能に
一定額までであれば家庭裁判所の判断なしに直接、金融機関から預貯金を引き出せるようになった。申立てをいらないので、各自相続人にとっては負担が小さい。
第九〇九条の二(遺産の分割前における預貯金債権の行使)
各共同相続人は、遺産に属する預貯金債権のうち相続開始の時の債権額の三分の一に第九百条及び第九百一条の規定により算定した当該共同相続人の相続分を乗じた額(標準的な当面の必要生計費、平均的な葬式の費用の額その他の事情を勘案して預貯金債権の債務者ごとに法務省令で定める額を限度とする。)については、単独でその権利を行使することができる。この場合において、当該権利の行使をした預貯金債権については、当該共同相続人が遺産の一部の分割によりこれを取得したものとみなす。
このうち、「法務省令で定める額」は150万円とされた(民法909条の2に規定する法務省令で定める額を定める省令(平成30年法務省令第29号))。つまり、金融機関ごとに上限150万円までは、相続人が単独で払戻しが受けられる。
(3)相続の効力等に関する対抗要件制度
これについて詳しくは、事例も踏まえて、詳しく別稿で述べる。
新しい条文は下記のとおりである。
第八九九条の二(共同相続における権利の承継の対抗要件)
相続による権利の承継は、遺産の分割によるものかどうかにかかわらず、次条及び第九百一条の規定により算定した相続分を超える部分については、登記、登録その他の対抗要件を備えなければ、第三者に対抗することができない。
2前項の権利が債権である場合において、次条及び第九百一条の規定により算定した相続分を超えて当該債権を承継した共同相続人が当該債権に係る遺言の内容(遺産の分割により当該債権を承継した場合にあっては、当該債権に係る遺産の分割の内容)を明らかにして債務者にその承継の通知をしたときは、共同相続人の全員が債務者に通知をしたものとみなして、同項の規定を適用する。
要するに、相続させる旨の遺言等により承継された財産については、登記なくして第三者に対抗することができるとされていた改正前民法の実務を見直し、法定相続分を超える権利の承継については、対抗要件を備えなければ第三者に対抗することができないようにする。遺言制度よりも、第三者との取引の安全を重視するという考えからの改正である。
遺産である不動産については、相続または法人の合併による権利の移転の登記は、登記権利者が「単独で」申請することができる(不動産登記法63条2項)。
仮に、父親が、「長男に全財産を相続させる」という遺言(特定財産承継遺言)を残して亡くなったときに、相続人が長男と次男のみとすると、遺言の存在を知っていた次男が、素早く自分の法定相続分を登記したうえで、それを第三者に譲渡して移転登記すれば、第三者が次男の法定相続分につき完全な権利を得てしまうので、長男は、自分の法定相続分を超える分について、第三者に対し、「それは自分のものだ」と主張することはできなくなった。
ただ、一方で、民法1013条には、「遺言執行者がある場合には、相続人は、相続財産の処分その他遺言の執行を妨げるべき行為をすることができない」(同法1項)、「前項の規定に違反してした行為は、無効とする。ただし、これをもって善意の第三者に対抗することができない」(同法2項)という条文があるので、悪意の次男との関係では無効になるが、第三者が、この父親の遺言の存在および遺言執行者の指定があることを知らなかった時には、法定相続分を超える分に自分のものだという主張ができなくなる。
もっとも、次男の不動産に対する相続登記そのものが、法で相続人の単独申請ができるとしているので、これそのものを遺言の執行の妨害行為と言えない可能性が高い。専門家を遺言執行者に指定したうえで、遺言者の死亡と同時に、速やかに遺言手続を行うしか方法がなかろう。
このことは、第2項にあるように、預貯金債権等も同じく対抗要件が必要である。また預貯金の払戻しの請求およびその預貯金に係る契約の解約の申入れをすることができる。
いずれにしろ、遺言執行業務の重要性とリスクは高まったといえる。
一部の専門家や信託銀行の「しばらく様子を見てから遺言執行を開始する」という手法はもう過去のものだ。
仮に、相続人による、不動産に対する法定相続分の相続登記や預貯金債権の払戻し、差押え等を許してしまうと、どうなるのか。
遺言が一部執行できなくなり、最悪、相続人による法的責任追及など困った事態に発展しないともいえない。遺言執行者が遺言で指定されれば通常は遺言公正証書の正本と謄本双方を預かる場合が多い。受遺者である相続人は登記ができない例も少なくなかろう。
しかも法改正で遺言執行者の権限は強化された。
悠長な執行で対抗要件で負ければ、できるのにしなかったとなり、委任契約の善管注意義務を怠ったとの責任追及も考えられる大きなリスクがある。
7.配偶者の居住権を保護する法改正
これについても、詳しく述べた。参照にされたい。
相続時の建物敷地を、妻が取得する「配偶者居住権」と子どもが相続する「負担付き所有権」に分割し、その負担消滅時までは子どもはその建物敷地を利用できずその期間の収益は得られないことになった
配偶者居住権は、基本的に、遺産分割の場で認められる権利であるが、改正法は「配偶者居住権が遺贈の目的とされたとき」とも定めたので、遺言によっても設定が可能で、また、遺贈として扱われる死因贈与契約でも取得させることができる。
しかし、配偶者居住権を遺言で設定するにあたっては、残される配偶者と他の相続人(特に負担付き所有権を取得する相続人やその家族)との折合いなど家族関係、相続財産における自宅不動産の経済的価値の割合、配偶者の不動産を適正に利用する仕方などを総合的に考慮する必要があるので、遺産分割の場での話にしたほうがいいのでないか。
配偶者居住権は、当事者の信認関係に裏打ちされた制度と考えられているからだ。
子である負担付き所有権者は使用収益ができないにもかかわらず、公租公課や各種修繕費用を負担する。納得できない場合もあろう。その負担は、相続税から始まり、固定資産税、大規模修繕費など、軽くはない場合もある。
なお、配偶者居住権の合理的な節税対策としての利用も話題となっている。配偶者居住権は、生存配偶者の死亡により消滅するため、実の親子など、配偶者からその子などへの第二次相続では相続税はかからないと考えられるためだ。
8.特別寄与者への特別寄与料給付制度
これについても、詳しく述べた。
この制度では、要件が、特別寄与者にとって厳しい。特別寄与料を受け取るためには、特別寄与者自身が請求しなければ支払われないこと(当然金額も算定)、そのためには相続人との協議が必要なこと、請求期開か大変短いことなどである。
長男が亡くなった後で義母などの世話をした「長男の嫁」のような者がいる場合に、特別寄与者が、被相続人に対して無償で労務の提供をしたことや、被相続人の財産の維持増加にどれだけ貢献したかについて、立証や算定が難しい。
やはり、「長男の嫁」の貢献に報いたいという気持ちがあるのなら、生前のうちに一定割合を遺贈する旨の遺言をするのがいいのでないか。
投稿者プロフィール

最新の投稿
 相続全般2024年6月3日相続ワンストップサービス 相続おもいやり相談室へ
相続全般2024年6月3日相続ワンストップサービス 相続おもいやり相談室へ 遺留分2024年4月27日相続対象不動産の生前名義変更と遺留分侵害
遺留分2024年4月27日相続対象不動産の生前名義変更と遺留分侵害 財産管理2023年11月12日実務家のための相続財産の調査【令和5年最新版】
財産管理2023年11月12日実務家のための相続財産の調査【令和5年最新版】 遺産分割2023年5月21日【遺産分割10年規制】とは? 相続法の改正 令和5年4月1日施行
遺産分割2023年5月21日【遺産分割10年規制】とは? 相続法の改正 令和5年4月1日施行