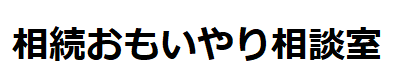1.改正相続法の下での事例検討
■事例
Aが遺言書を作成する場合や作成して遺言執行段階において、次のような場合は、相続人と遺言執行者との利益相反行為が発生するか。なお、Aの遺産は不動産及び預金で、法定相続人は、配偶者Bおよび子Cである。
(1) Aが、Bに遺産の4分の3、Cに4分の1の割合で遺産を相続させる旨の公正証書遺言を作成する場合、 AはBを遺言執行者に指定することができるか。
(2) Aが、認知していた非嫡出子Dに全遺産を遺贈する旨の遺言を作成する場合、 AはDを遺言執行者に指定することができるか。
(3) Aは、遺言執行者は不動産を売却するなどして換価し、これをまず家のローン残債務の弁済に充てたうえで、 その残額をBとCに等分にて相続させる旨の遺言を作成してDを遺言執行者に指定した。 その後、 Aが死亡し、Dが遺言執行者に就任した場合、 Dは自らを買主として当該不動産を売却することはできるか。
2.改正前の相続法での結論
(1)可能である。
この場合に、遺言執行者を「相続人の代理人」とする法律構成では、法定相続分より少なくなる相続人Cに対する利益相反行為であり、違法な双方代理的な立場にBはおかれるので、相続人であるBを遺言執行者にすることは許されないことになろう。
…………………………………………………………………………………………………………………
【民法】第一〇八条(自己契約及び双方代理等)
同一の法律行為について、相手方の代理人として、又は当事者双方の代理人としてした行為は、代理権を有しない者がした行為とみなす。ただし、債務の履行及び本人があらかじめ許諾した行為については、この限りでない。
2前項本文に規定するもののほか、代理人と本人との利益が相反する行為については、代理権を有しない者がした行為とみなす。ただし、本人があらかじめ許諾した行為については、この限りでない。
…………………………………………………………………………………………………………………
しかし、遺言執行者は、実質的には「遺言者の代理人」であり、しかも単なる債務履行類似の行為であり、上記の法条の但し書きに相当するものと言えよう。
また、遺言執行者の欠格事由として法は次のように定めるのみだからである。
…………………………………………………………………………………………………………………
第一〇〇九条(遺言執行者の欠格事由)
未成年者及び破産者は、遺言執行者となることができない。
…………………………………………………………………………………………………………………
(2)可能である。
(1)で述べたことがそのまま受遺者にも当てはまろう。より相続人との利益相反的な状況が厳しくなる。
(3)できない。
この場合は、債務の履行として解釈できることを超えて、自己契約そのものであり、民法108条ができないものとして類型化したものに相当し、例えば安い値段で買うなど新たな不利益を相続人にもたらす可能性が出てくるからである。
3.改正相続法の下での結論
改正論議の中で、遺言執行者に「相続人」や「受遺者」を欠格事由として追加すべきかが議論されたが、理論的にも現状の実務を尊重する立場からもそうならなかったのは周知のとおりである。
そこで、やはり相続人の廃除の遺言の執行のように相続人の利益に反する行為も可能なことから、結論的には変わらない。
もっとも、遺言執行者の権限は強化され(1013条等)、より遺言者の代理人として性質が強くなっていても、もしも明らかな利益相反的な行為をすれば、解任も可能である。
…………………………………………………………………………………………………………………
第一〇一九条(遺言執行者の解任及び辞任)
遺言執行者がその任務を怠ったときその他正当な事由があるときは、利害関係人は、その解任を家庭裁判所に請求することができる。
2遺言執行者は、正当な事由があるときは、家庭裁判所の許可を得て、その任務を辞することができる。
…………………………………………………………………………………………………………………
(1)可能である。
(2)可能である。
(3)出来ない。なお、1015条は遺言執行者の行為の効果として、「遺言執行者がその権限内において遺言執行者であることを示してした行為は、相続人に対して直接にその効力を生ずる。」としていても、108条の適用を排除するものではなかろう。
(一問一答 新しい相続法 商事法務、Before/After 相続法改正 弘文堂、ジュリスト 2018年12月号等参照)
投稿者プロフィール

最新の投稿
 お知らせ2025年5月13日中川総合法務オフィスは統合サイトに全て移行中。
お知らせ2025年5月13日中川総合法務オフィスは統合サイトに全て移行中。 相続全般2025年4月2日相続(特に遺産分割)におけるエンバーミングの必要性
相続全般2025年4月2日相続(特に遺産分割)におけるエンバーミングの必要性 相続全般2025年2月28日世話していた独身の叔父さんが2億円を残して急死。いとこが何人いるか不明。どうすればいいのか【相続実例】
相続全般2025年2月28日世話していた独身の叔父さんが2億円を残して急死。いとこが何人いるか不明。どうすればいいのか【相続実例】 相続全般2025年2月9日墓のある相続土地の売却方法は4つほどある:相続おもいやり相談室
相続全般2025年2月9日墓のある相続土地の売却方法は4つほどある:相続おもいやり相談室