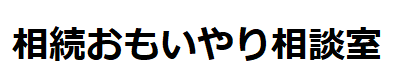1.遺言書の持参
(1)遺言の有効性
まず何といっても相続おもいやり相談室でいつも説明会やパンフレットで言っている通り、「民法に定める方式よる遺言」である(民法960条)ことが不可欠である。
仮に、後に実は遺言当時にアルツハイマー型認知症で遺言能力がなかったので無効とされる自筆証書遺言等でも金融機関が民法の方式を満たす形式があれば、「債権の準占有者に対する弁済」(債権法改正後は「受領権者としての外観を有する者に対する弁済」民法478条)として認められるので善意無過失の金融機関は支払う。
なお、遺留分を侵害するような遺言書であっても(例えば内縁の妻、神社仏閣、慈善団体などに全て遺贈する場合には、被相続人の死亡時点で当該預貯金等の権利者は当該第三者となる)、法定相続人は受遺者に対して改正法の遺留分侵害額の請求(民法1046条1項)を行うことはできるが、当該預貯金等については無権利者であるので、金融機関による払戻しはなされる。もっとも、すでに、法定相続人が遺留分減殺請求権を行使している場合もあろうが、2019年7月1日以降であれば侵害額の請求権に変化しているので、やはり金融機関は慎重であるものの支払うであろう。
この点について、これまで何度も現物の遺言書を持参されて法律相談を受けたが、遺言執行者の定めがあれば、その法的手続きを踏んで、法定相続人への就任と遺言内容等の連絡をきちんと行うのが前提であろう。なし崩しに自分のモノにできる場合もあろうが、相続おもいやり相談室ではそういうことは一遍もしたことがないし相談者へも絶対やめるように申し上げている。時々、他の法律家等は黙っておればわからないとかいうことも多いそうであるが。全く腹立たしいことで、そこには正義の片鱗もない。当職も引き続き故末川博大学総長の教えに従ってこの世の一隅を照らす「生涯一法学徒」を続けたい。
(2)遺言書の存在性
しばしば、遺言書はその存在が不明である。遺言者の死亡後暫くして、場合によっては1年ほどたってから出てくるのも実務ではあるのだ。もう遺産分割も相続登記も払戻も終わっている。
では、遺言の存在を知らずに金融機関は払戻請求に応じてしまった場合にも、遺言書で多くの割合をもらえることになっていた相続人などは再度払ってほしいといえるであろうか。
これは先述の「債権の準占有者に対する弁済」(債権法改正後は「受領権者としての外観を有する者に対する弁済」)の問題である。
判例は、「銀行側としては当該預金の払戻を請求した相続人が正当な相続人であることを確認するほか、特段の事情のない限り預金者である被相続人の遺言の有無については、払戻の請求をした相続人に対して一応確かめれば足り、それ以上、別の調査をする義務はなく、これをしないでも払戻について過失があるということはできない」としている(東京高判昭和43・ 5 ・28)。
なお、遺言はいつでも撤回できるので(民法1022条)、最新の遺言の存在を知らずに撤回された遺言に従い払戻請求に応じてしまった金融機関に、本来の権利がある最新の遺言の相続人などが支払いを請求できるかも上記の判例の基準になろう。
2.遺言について「争い」はないか
これは当職も実務でいつも細心の注意を払うところである。というのは、金融機関は争いを嫌がるからである。不用意な遺言執行者の発言で払い戻しがストップすることもあるようだ。当職はいまだに経験していないが、ある話である。
金融機関は、争いがある事情を把握した場合には、まず、その争いの内容が、遺言の内容についての単なる不平・不満にすぎないのか、それとも、遺言書の有効性についての争いなのかを判断しようと乗り出してくる。厄介なことになってくるのだ。
その争い内容が、遺言の偽造が合理的に疑われる等遺言書に疑義が生じた場合は、訴訟や調停の結果が出るまでは、預貯金等の払戻請求に応じない。
しかし、銀行は銀行でジレンマに入ってくるのだ。当事者から預貯金の払戻しを請求されて無効な払戻請求に応じたときの「二重払いリスク」と、有効な払戻請求を拒んだときに「遅延損害金を負担するリスク」ジレンマである。
供託をしてくる場合もあろう。
遺言執行者が自信があれば、遺言の内容や当事者の親族関係等の総合的な事情を申し上げて催促するしかなかろう。両者の誠実性の問題である。
投稿者プロフィール

最新の投稿
 お知らせ2025年5月13日中川総合法務オフィスは統合サイトに全て移行中。
お知らせ2025年5月13日中川総合法務オフィスは統合サイトに全て移行中。 相続全般2025年4月2日相続(特に遺産分割)におけるエンバーミングの必要性
相続全般2025年4月2日相続(特に遺産分割)におけるエンバーミングの必要性 相続全般2025年2月28日世話していた独身の叔父さんが2億円を残して急死。いとこが何人いるか不明。どうすればいいのか【相続実例】
相続全般2025年2月28日世話していた独身の叔父さんが2億円を残して急死。いとこが何人いるか不明。どうすればいいのか【相続実例】 相続全般2025年2月9日墓のある相続土地の売却方法は4つほどある:相続おもいやり相談室
相続全般2025年2月9日墓のある相続土地の売却方法は4つほどある:相続おもいやり相談室