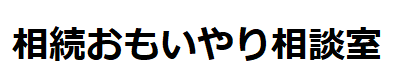1.相続法の改正
これについては、すでに詳しい法改正の内容全体をこのブログに書いた。
そこでここでは、実務家向けに特に私の多くの業務を占める「遺言、遺言執行」実務への多大な影響について述べたい。
2.相続法改正と遺言(相続)実務への影響
(1)相続法改正と施行日
2018年7月、相続に関する民法の規定がー部改正され、2019年7月1日から施行された。
もっとも、自筆証書遺言の方式緩和については2019年1月13日から、配偶者居住権については2020年4月1日からの施行となった。また自筆証書遺言の保管制度は2020年7月10日施行である。
(2)遺産争い防止のための遺言制度活用
最高裁の司法統計による資料(平成19年)

財産が、1千万円以下でも全体の約3割が紛争となり、5千万円以下であればおおよそ4分の3が紛争となっている。このことから、財産が多い少ないにかかわらず、相続放棄するべき様な債務が多くない限り、紛争が発生している。
被相続人が亡くなった後の遺産分割において、特に当職に多い相談が、「遺産がマイホームだけ、若しくは不動産ととわずかな預貯金だけ」というケースである。とても着手金はもらえないので、受理も難しいケースが多い。案件が全て片付いてからの後払いとなる。
とりあえず3つの解決法があるのでそれを提示していつも相談に乗っている。
①不動産を売却して金銭分割する。
②相続人のうち誰かが不動産を相続し、代償金を他の相続人に払う。
③共有名義にしておく。
しかし、①の合意を全員がすることは難しい場合が多い。
なぜなら、地方で売れない場合、そこにだれか住みたい場合、土地や家への思い入れがある場合、そもそも今現在誰かが住んでいる場合などは特にそうである。
②も解決策としてすぐに結論が出ない場合が多い。何といっても、代償金相当の金をまとめて払えることが難しいケースが圧倒的である。
③はもちろん、そのうちの誰かが亡くなれば共有者が増えて、将来、売却や賃貸の際に意思決定が難しく、権利関係が複雑に日増しになっていくのであって、一時的なその場しのぎであろう。
自分の財産の行方は関心がないとすれ遺族が紛争で悲しみ、トラブルで時間とお金がとられるばかりである。
専門家と作った遺言があれば、完全ではないが、ほぼこのような紛争はなくなろう。1千万円以下の財産であれば、いざ調停や訴訟になった場合に、遺族に弁護士費用の負担も発生する。
財産の多い人は、生前贈与なども含めて対策しているが、少ない人は油断するのでトラブルが発生しやすともいえよう。
(3)財産の行方の明快さと遺言執行の容易さ
権利者が増えれば増えるほど調整が難しくなるが、預貯金の相続割合、株式等の有価証券の処分方法、不動産を相続する相続人などの決定、自動車を誰に渡すかなどをもしも何も決めておかなければ、原則として全員の戸籍謄本や実印、署名が必要になってくる。銀行によってもやり方は様々で、いくつも原本を取り寄せる必要が出てくる。
当職も何度も経験したが、相続人が高齢だったり、痴呆の症状が出てきていたり、入院中であったり、海外に住んでいたり、幼い子どもを抱えていたり、あるいは平日役所に行く時間がとれないサラリーマンや公務員などは、相続手続の負担が非常に大きい。
また、当職によく依頼のあるのが、途中までやってみたが大変だったので残りの手続きをやってくれというのも結構ある。新規に登場した当職を戸惑う当事者が出てくる。
もしも、遺言と執行する人の指定があれば、預貯金や不動産など遺産の種類が多かったり、相続人がたくさんいたりする場合でも、原則として遺言で指定された人だけの手続になるので迅速で、必要書類を集める手間や他の相続人の同意を得る時間がかなり短縮できる。
また、「付言」などで当職がよく使う方法に、なぜにこのような財産分けになるのかを書いておけば、当事者の話し合いで嘘も付けないであろう。
先ほど述べた、今現在住んでいるものに引き続き住んでほしいのに、遺言で指定がなければ法定相続分による共有になろうが、安心して住めなくなってしまう。(配偶者居住権はこのための制度だが選択は任意)
(4)自筆証書遺言に関する相続法改正
この遺言は遺言をする人自身が、全文を自筆で書き、署名・押印することで完成させる遺言であったが、法改正により、財産目録についてはパソコンなど自書以外の方法で作成することも可能になった(民法968条2項)。
しかしながら、本文を自筆で書く必要があり、病気や加齢により手や目が不自由になり、文字が書けなくなった人は、この方式によることができないことは変わりない。
この遺言は、手軽に誰に知られずに作成できることが利点であるが、民法の定める方式を少しでも間違えると無効になる、遺言書を作ったことを秘密にしていると、死後発見されない、紛失や第三者による改ざん、破棄等のおそれがある。
また、最も面倒なのは死後、家庭裁判所の検認手続が必要になことであろう。死後の手続の問題として、戸籍謄本などの必要書類を集めて提出したあと、裁判所から相続人全員に呼出状が送付され、指定日に裁判所で検認手続が行われるため、準備も含めて数力月程度の時間がかかり、その間は相続手続ができない。
なお、「検認」とは、相続人に遺言の存在と内容を知らせるとともに、検認の日現在における遺言書の内容を明確にして遺言書の偽造・変造を防止するための手続で、誤解が多いが、遺言の有効・無効を判断する手続ではない。
また、遺言は新しいものほど有効なので、亡くなる直前に重要な遺言を撤回したり書き換えたりしてしまい、相続人が困る場合がある。さらに、法律用語や内容に間違いがあり、遺言が執行できない場合、京都のかばん屋さん事件のように死後、遺言書の有効性をめぐって争いになりやすいのである。
自筆という性質上、その遺言書が本当に本人によって書かれたものかどうかが問題になりやすく、鑑定人の意見もしばしば分かれる。
自筆と認められた場合でも、誰かに無理やり書かされたものではないか、書いた時点ですでに本人が認知症等で判断能力が低下していたのではないかなどの疑いをもたれて、裁判で有効性が争われることも少なくない。
かりに、自筆証書遺言が無効となれば、遺言がないものとして、原則どおり、相続人全員が遺産分割協議を行わなければならなくなる。
もっとも、判例実務では、遺言をなるべく有効にしようと解釈すべきとされている。そこで、遺言者の意思の合理的推定をすべきであろう。
例えば、「運筆について他人の添え手による補助を受けてされた自筆証書遺言は、⑴遺言者が証書作成時に自書能力を有し、⑵他人の添え手が遺言者の手を用紙の正しい位置に導くにとどまるか、又は支えを貸したにすぎないものであり、かつ、⑶添え手をした者の意思が介入した形跡のないことが筆跡の上で判定できる場合には、「自書」の要件を満たし有効である。(最判昭62・10・8)とされる。
自筆証書遺言が公正証書遺言と違って、一つしかないので遺言書の改ざんや紛失を防ぐための方策がなかったが法務局で自筆証書遺言を保管する制度が2020年7月1日から始まったが利用は任意である。当職もお話ししてお勧めするが、10人に一人くらいの方しか乗り気にならない。
投稿者プロフィール

最新の投稿
 お知らせ2025年5月13日中川総合法務オフィスは統合サイトに全て移行中。
お知らせ2025年5月13日中川総合法務オフィスは統合サイトに全て移行中。 相続全般2025年4月2日相続(特に遺産分割)におけるエンバーミングの必要性
相続全般2025年4月2日相続(特に遺産分割)におけるエンバーミングの必要性 相続全般2025年2月28日世話していた独身の叔父さんが2億円を残して急死。いとこが何人いるか不明。どうすればいいのか【相続実例】
相続全般2025年2月28日世話していた独身の叔父さんが2億円を残して急死。いとこが何人いるか不明。どうすればいいのか【相続実例】 相続全般2025年2月9日墓のある相続土地の売却方法は4つほどある:相続おもいやり相談室
相続全般2025年2月9日墓のある相続土地の売却方法は4つほどある:相続おもいやり相談室