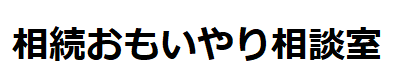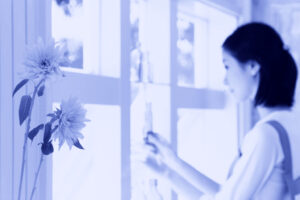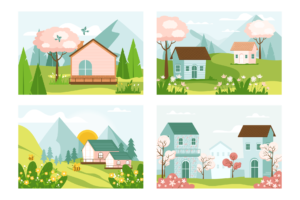司法試験 令和4年〔第34問〕
Aの相続財産の取得に関する次のアからオまでの各記述のうち、判例の趣旨に照らし正しいものを組み合わせたものは、後記1から5までのうちどれか。
ア.甲土地の共有持分がAの相続財産に属する場合において、Aに相続人がおらず、かつAの債権者も受遺者もいないときは、その持分は他の共有者に帰属し、特別縁故者への分与の対象とならない。
イ.相続開始後にAの子と認知されたBが遺産分割を請求した場合において、他の共同相続人が既に遺産分割をしていたときは、その遺産分割は、効力を失う。
ウ.AからAの相続財産に属する乙土地の遺贈を受けたCは、Aが死亡した後いつでも遺贈の放棄をすることができる。
エ.Aの相続財産に属する丙土地を無償で管理していた特別寄与者であるDは、その寄与に応じ、丙土地の持分を取得することができる。
オ.Aの親族でないEは、無償でAの療養看護をしたことによりAの財産の維持に特別の寄与をしても、特別寄与者には当たらない。
1.アイ 2.アオ 3.イエ 4.ウエ 5.ウオ
ア. × 間違いです。「共有者の一人の相続が開始し相続人がいないとき、その共有持分は特別縁故者に対する分与の対象となり、特別縁故者もいないことが確定したときにはじめて民法二五五条により他の共有者に帰属する。(最判平元・11・24)」
イ. × 間違いです。第九一〇条「相続の開始後認知によって相続人となった者が遺産の分割を請求しようとする場合において、他の共同相続人が既にその分割その他の処分をしたときは、価額のみによる支払の請求権を有する。」
ウ. ○ その通りです。 第九八六条「① 受遺者は、遺言者の死亡後、いつでも、遺贈の放棄をすることができる。」
エ. × 間違いです。1050条にある通り、金銭請求のみである。
オ. ○ その通りです。 同じく、親族のみが請求できる。
●正解 5
投稿者プロフィール

最新の投稿
 相続全般2024年6月3日相続ワンストップサービス 相続おもいやり相談室へ
相続全般2024年6月3日相続ワンストップサービス 相続おもいやり相談室へ 遺留分2024年4月27日相続対象不動産の生前名義変更と遺留分侵害
遺留分2024年4月27日相続対象不動産の生前名義変更と遺留分侵害 財産管理2023年11月12日実務家のための相続財産の調査【令和5年最新版】
財産管理2023年11月12日実務家のための相続財産の調査【令和5年最新版】 遺産分割2023年5月21日【遺産分割10年規制】とは? 相続法の改正 令和5年4月1日施行
遺産分割2023年5月21日【遺産分割10年規制】とは? 相続法の改正 令和5年4月1日施行