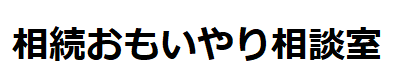相続の現場においては、相続税法の概略は不可欠になってきているであろう。これは、平成28年の改正の影響がやはり大きい。京都や大阪での相続おもいやり相談室の相談でも、相続税・贈与税の計算方法についての突っ込んだ質問がなされるようになってきた。10年前には及びもつかなかった話である。なお、3年前贈与だけでなく、7年前からのものも相続税の対象とするなどの大きな法改正が令和5年以降に予定されている。別稿で述べる。
1.相続税法
相続税法は、贈与税も含めた法律で、全部で71条ある。
比較的わかりやす法律の部類に入るであろう。
相続税の考え方には、残された遺産そのものを課税対象とする「遺産税」と遺産を取得したことにより相続人などの担税力が増加したことに着目して課税する「遺産取得税」の考え方があるが、わが法は折衷法である。
【目次】
第一章 総則
第一節 通則(第一条―第二条の二)
第二節 相続若しくは遺贈又は贈与により取得したものとみなす場合(第三条―第九条)
第三節 信託に関する特例(第九条の二―第九条の六)
第四節 財産の所在(第十条)
第二章 課税価格、税率及び控除
第一節 相続税(第十一条―第二十条の二)
第二節 贈与税(第二十一条―第二十一条の八)
第三節 相続時精算課税(第二十一条の九―第二十一条の十八)
第三章 財産の評価(第二十二条―第二十六条の二)
第四章 申告、納付及び還付(第二十七条―第三十四条)
第五章 更正及び決定(第三十五条―第三十七条)
第六章 延納及び物納(第三十八条―第四十八条の三)
第七章 雑則(第四十九条―第六十七条の二)
第八章 罰則(第六十八条―第七十一条)
※二十一条の九以下の規定は、実務よく話題になる納税者の選択により、被相続人が生存中に行う一定の「推定相続人」への贈与に暫定的に贈与税を課し、被相続人の死亡時の相続税の課税対象にこの贈与財産を含めつつ、先行する暫定的な贈与課税を相続税額の計算において精算する、「相続時精算課税制度」であり、平成15年改正において設けられた。実務上は一定の利用がある。
相続税は、相続または遺贈により財産を取得した個人を納税義務者とする国税である。
相続と遺贈は原則として同じ扱いを受け、死因贈与は遺贈に含まれる。
公平性から実際の課税は以下のような2段階制をとっている。
法定相続分課税方式といって最初に遺産に係る「相続税の総額」を算出し、次にその総額を各相続人等が実際に相続等により取得した財産の額に応じて各相続人等に割り当てるのである。
(1)同一の被相続人に係るすべての相続人等について、取得した財産で課税対象となるものの総額から被相続人の債務等(相続開始の際に現に存する債務で確実と認められるものと葬式費用)でその相続人等の負担に属する部分の金額を控除した残額が課税価格である。
合計額から遺産にかかる基礎控除を行い、法定相続分によって取得したものとみなし税率表を適用して個々人の税額を計算した合計が相続税の総額である。
(2)相続税の総額を、相続人等が現実に取得した課税価格に応じて按分し、被相続人の配偶者であること、相続人等が未成年であることなどの事情に応じて税額を軽減したり、相続人等が被相続人の1親等の血族および配偶者以外である場合に税額を20%割り増したりする調整を行う。下記は法16条の総額算出相続税率である。
| 千万円以下の金額 | 百分の十 |
| 千万円を超え三千万円以下の金額 | 百分の十五 |
| 三千万円を超え五千万円以下の金額 | 百分の二十 |
| 五千万円を超え一億円以下の金額 | 百分の三十 |
| 一億円を超え二億円以下の金額 | 百分の四十 |
| 二億円を超え三億円以下の金額 | 百分の四十五 |
| 三億円を超え六億円以下の金額 | 百分の五十 |
| 六億円を超える金額 | 百分の五十五 |
| 法定相続分に応ずる取得金額 | 税率 | 控除額 |
|---|---|---|
| 1,000万円以下 | 10% | - |
| 3,000万円以下 | 15% | 50万円 |
| 5,000万円以下 | 20% | 200万円 |
| 1億円以下 | 30% | 700万円 |
| 2億円以下 | 40% | 1,700万円 |
| 3億円以下 | 45% | 2,700万円 |
| 6億円以下 | 50% | 4,200万円 |
| 6億円超 | 55% | 7,200万円 |
※国税庁の計算サイト https://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/4155.htm
◆簡単な例題 http://www.tokyozeirishikai.or.jp/general/zei/souzoku/
◆参考(法21条の7の贈与税率)
| 二百万円以下の金額 | 百分の十 |
| 二百万円を超え三百万円以下の金額 | 百分の十五 |
| 三百万円を超え四百万円以下の金額 | 百分の二十 |
| 四百万円を超え六百万円以下の金額 | 百分の三十 |
| 六百万円を超え千万円以下の金額 | 百分の四十 |
| 千万円を超え千五百万円以下の金額 | 百分の四十五 |
| 千五百万円を超え三千万円以下の金額 | 百分の五十 |
| 三千万円を超える金額 | 百分の五十五 |
贈与税の速算表
■親から成人の子へ等【特例贈与財産用】(特例税率)
| 基礎控除後の課税価格 | 200万円 以下 | 400万円 以下 | 600万円 以下 | 1,000万円 以下 | 1,500万円 以下 | 3,000万円 以下 | 4,500万円 以下 | 4,500万円 超 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 税 率 | 10% | 15% | 20% | 30% | 40% | 45% | 50% | 55% |
| 控除額 | ‐ | 10万円 | 30万円 | 90万円 | 190万円 | 265万円 | 415万円 | 640万円 |
【一般の贈与税(上以外)】
| 基礎控除後の課税価格 | 200万円 以下 | 300万円 以下 | 400万円 以下 | 600万円 以下 | 1,000万円 以下 | 1,500万円 以下 | 3,000万円 以下 | 3,000万円 超 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 税 率 | 10% | 15% | 20% | 30% | 40% | 45% | 50% | 55% |
| 控除額 | ‐ | 10万円 | 25万円 | 65万円 | 125万円 | 175万円 | 250万円 | 400万円 |
◆簡単な例題 http://www.tokyozeirishikai.or.jp/general/zei/souzoku/
2.相続税の例外等
(1)相続開始前3年以内に贈与があった場合
相続人等が相続開始前3年以内に被相続人から贈与を受けていた場合は、その贈与を受けた価額を相続税の課税価格に算入した相続税額から納付済みの贈与税額を控除する。
富の蓄積への公平な課税のためである。
(2)相次相続控除(そうじ…)
Aが死亡してBが相続等により財産を取得して相続税を負担し、さらにBが死亡してCが相続等により財産を取得した場合に、Aの死亡がBの死亡(相続開始)前10年以内であれば、Cが負担する相続税額からBが納付した税額の一部を控除する、
同じ財産に短期間に何度も課税するのを防ぐ。
(3)小規模宅地の負担軽減措置(租税特別措置法69条の4)
被相続人が事業または居住の用に供していた宅地を、被相続人の配偶者や同居の親族等が相続等により取得した場合に、一定面積(事業用は400㎡以下、居住用は330㎡以下)まではその評価額の80%を課税価格に算入しない(20%のみを課税価格に算入する)とする措置がある。
居住や事業継続のための政策規定である。
3.課税物件
(1)非課税財産
納税者の課税価格に含まれるのは、相続等により取得した財産であるが、「墓所、霊びよう及び祭具」等、[宗教、慈善、学術その他公益を目的とする事業を行う者]が取得した財産で公益目的事業に供することが確実なものなど、法定の非課税財産に該当するものは、課税価格に算入しない。
(2)みなし相続財産
①保険料を被相続人が負担した保険金、被相続人の死亡後3年以内に支給が確定した退職手当金、ただしこの二者は相続人の人数に500万円を乗じた額を上限とする非課税枠がある。また民法958条の3第1項により特別縁故者に対して分与された相続財産。
②遺言によりなされた財産の低額譲受、債務の免除、債務引受または第三者のためにされた弁済、その他無償または低額で利益を受けた場合、委託者の死亡により効力を生じた信託受益権等。
4.財産等の評価
(1)財産の評価
法は、財産の価額は、当該財産の取得の時における時価によることを評価の原則としているので、「時価」概念が確定する必要がある。
ある判例は、時価とは課税時期において不特定多数の当事者間で自由な取引が行われた場合に通常成立する価額としているのが参考になろう(東京高判平7・12・13)。
しかし、評価方法を具体的に定めているのは、地上権、永小作権と定期金に関する権利のみであるため、国税庁は「財産評価基本通達」を定めて公表し、財産の評価をこの通達に基づいて一律に行っている(相続が発生するごとに相続財産に含まれる土地の鑑定を行うというような個別的な方法ではない)。
もっとも評価の安全を見込むため、現実の取引価格よりもある程度低めの価格を評価額とする。
(2)土地の評価
土地は、宅地、田、畑などの10種類の地目ごとに、原則として1区画を単位として評価され、通常は市街地を形成している地域は路線価方式、それ以外の地域は倍率方式である。
路線価方式とは、毎年、市街地の主要な街路ごとに「1㎡当たり幾ら」という「路線価」を設定しておいて、その街路に面している宅地はこの路線価に面積を乗じ、さらにその土地の形態などに応じた加算・減算を行って土地の評価額を決定する方法である。
取引価格の約8割の水準とされている。
市街地を形成していない地域における土地の評価には倍率方式が用いられる。
市町村長が決定する固定資産税賦課に用いる評価額に国税局長が決めた一定の倍率を乗じて評価額を決定する方式である。
しかし、取引価格とのかい離が激しい場合が多く租税回避へのバイアスがかなり強くかかってくるので裁判所は近時修正判決が出ていることに注意する必要があろう。
(3)株式の評価(財産評価基本通達169以下)
株式および株式に関する権利は、銘柄ごとに、上場株式、気配相場のある株式、取引相場のない株式など10種類に分けて評価する。
上場株式は、相続開始の日の終値と、相続開始の日の属する月以前3ヵ月の毎日の最終価格を月ごとに平均した価格を比べて、最も低い価格で評価される。
この評価は株価の変動や操作を防止することができる。
問題は、取引相場のない株式であり、これらの株式は従業員数等の会社の規模を表す指標により「大会社」「中会社」「小会社」に区分して評価方法が定められている。
(4)債務の評価
課税価格の計算上控除し得る債務の評価はその時の現況によるので、控除すべき債務の評価額は当該債務の弁済すべき金額と一致するとは限らない。
5.潜脱的な税負担減少の防止(課税の公平)
(1)納税義務者の範囲に関する規定
相続人等(相続人・受遺者)の住所地と日本の国内財産を、どちらも国外に移せば、日本の相続税を潜脱することができるので、現行法は納税義務の範囲を拡大し、日本に住所を有しない者であっても、以下の①②については、日本に住所を有する者と同様に、国外財産を取得しても日本の相続税の納税義務を負うこととされた。
①相続人等が日本国籍を有する場合で、相続人等か被相続人の少なくともどちらか一方が、当該相続の開始前5年間に日本に住所を有していた場合
②相続人等が日本国籍を有しない場合で、被相続人が相続開始時に日本に住所を有していた場合
(2)養子を利用した租税回避への対処
相続人の人数が多い方が税額が減少するので、養子縁組を利用した相続税の回避の試みがなされた。
そこで、税法上は基礎控除などで相続人として人数に算入し得る養子の数を、被相続人に実子がある場合は最大1人、実子がいない場合は最大2人に制限している。
加えてこの制限内であっても、当該養子を相続人の人数に算入することにより相続税の負担を不当に減少させる結果となる場合には、税務署長が養子人数を制限し得る。
また、孫養子等については、被相続人の1親等の血族か配偶者以外の者の範疇に入れて20%加算の対象になることになっている。
なお、相続税の節税を目的にした養子縁組が有効かが争われた訴訟で、最高裁は平成29年1月31日、「節税のための縁組でも直ちに無効になるとは言えない」とする初判断を示し「相続税節税という動機と養子縁組に必要な『縁組の意思』は併存し得る」と指摘。今回は「縁組の意思がないことをうかがわせる事情はない」と判断して縁組を有効とした。
(3)持分の定めのない法人等に関する規定
公益法人等は、遺贈による利益について法人税を課税されないため、脱法的に持分の定めのない法人等(公益法人等)に対して遺贈がなされ、遺贈者の親族等の相続税の負担が不当に減少する結果となる場合には、当該法人を個人とみなして相続税が課税される。
(4)同族会社の利用に関する規定
3人以下の株主等により発行済株式の50%超が保有されている同族会社において、同族会社の行為計算がその株主・社員等の相続税の負担を不当に減少させる場合には、その行為計算を基礎とせず、税務署長の認めるところにより課税処分をなし得る。
6.確定・徴収手続
(1)申告と税額修正の手続
相続税は申告納税方式による国税であり、納税義務者は原則として、相続開始の日から10ヵ月以内に相続税の申告書を提出しなければならず、この日までに相続税額を納付しなければならない。
その際には、被相続人の死亡時の財産、債務、相続人等の全員についてそれぞれ取得した財産と承継した債務などを記載した明細書の添付が義務づけられているし、相続人等は一通の申告書に連署する共同申告しなければならない。
当面は相続人等の納税地は、相続人等の住所地ではなく、「被相続人の死亡の時における住所地」とされている。
法定申告期限までに遺産の全部または一部が未分割であった場合は、民法の規定による相続分又は包括遺贈の割合に従って財産を取得したものとして課税価格を計算し申告するが、法定相続分等とは異なる遺産分割がなされた場合には、修正申告(税額が増える場合)または更正の請求(税額が減る場合)により、税額を修正することができる。
認知、相続人の排除またはその取消しに関する裁判の確定、相続の回復などの事情により相続人に異動が生じれば、法定相続分課税方式の下では、各人の相続税額が変動する。
また、相続の放棄の取消し、遺留分減殺請求に基づき返還または弁償すべき額が確定したこと、遺贈に係る遺言書が発見されたこと、または遺贈の放棄があったことなども、相続人等の相続税額に影響を与える。税額修正の手続をおこなうことになる。
(2)連帯納付義務
同一の被相続人から相続等により財産を取得した者全員が、取得した利益の価額を限度として、相互に連帯納付義務を負うが、相続税の法定申告期限から5年内に連帯納付義務の履行が求められなかった場合などには連帯納付義務を負わない。
(3)延納と物納
納付すべき相続税額が10万円を超え、納期限までに金銭で納付することを困難とする事由がある場合には、納税者に原則として5年以内の延納を許可されて、毎年均等額を納付する。
相続財産に不動産が含まれる場合などは、延納期間をより長く設定し得る。
延納によっても税額を金銭で納付することが困難な場合には、その納税義務者の課税価格計算の基礎となった相続財産によって物納が許可される場合がある。
しかし、実際には管理処分不適格財産が物納対象から除かれ、物納できるとしても他の財産が優先される物納劣後財産の定め等があって制限が多い。
投稿者プロフィール

最新の投稿
 相続全般2024年6月3日相続ワンストップサービス 相続おもいやり相談室へ
相続全般2024年6月3日相続ワンストップサービス 相続おもいやり相談室へ 遺留分2024年4月27日相続対象不動産の生前名義変更と遺留分侵害
遺留分2024年4月27日相続対象不動産の生前名義変更と遺留分侵害 財産管理2023年11月12日実務家のための相続財産の調査【令和5年最新版】
財産管理2023年11月12日実務家のための相続財産の調査【令和5年最新版】 遺産分割2023年5月21日【遺産分割10年規制】とは? 相続法の改正 令和5年4月1日施行
遺産分割2023年5月21日【遺産分割10年規制】とは? 相続法の改正 令和5年4月1日施行